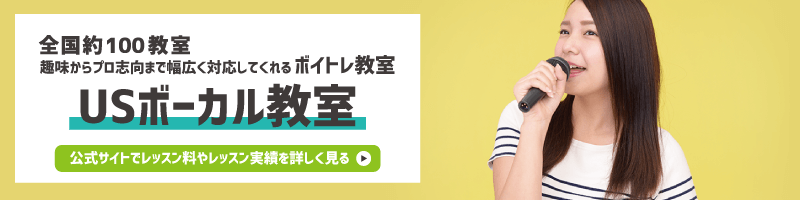ボイトレ専門用語 カテゴリ別索引
自主練習でYoutubeなどを見ている時によく使われているボイトレ用語、わからない言葉をそのままにしていませんか?知らなかった用語をわかるようにするだけでボイトレの成果が向上することもあります!
このページでは、ボイトレに関連のある専門用語をわかりやすく解説しています。探しやすいようにカテゴリー別に掲載し、同義語や類義語なども補足しています。このサイトで詳しく説明をしているページがある場合はリンクも貼っていますので、しっかり理解して日頃のボイトレ練習に役立ててください。
記号について
類義語:似た意味を持つ言葉。代替されることもある対義語:反対の意味を持つ言葉
同義語:同じ意味の言葉
呼吸
- 横隔膜
-
胸腔と腹腔の間にあるドーム状の筋肉。
胸部の下にあり、息を吸うと収縮して胸部が広がり肺を拡張して空気を取り込む。息を吐く時は横隔膜が弛緩して空気が吐き出される。横隔膜を意識した呼吸をすることで発声や声量の安定や表現力を向上させることができる。
- 胸式呼吸
-
肋間筋(胸のあたりにある肋骨と肋骨の間にある筋肉)を使って行う呼吸法。
肺を膨らませて呼吸を行うため深い呼吸をすると肩が上下するのが特徴。日常生活で活動しているときに行なっている主な呼吸。
腹式呼吸
- ドッグブレス
-
息を短く吐き出して横隔膜を鍛える呼吸法。
犬が小刻みに「ハッハッハッ」と呼吸する様子に似ていることからつけられた名称。腹式呼吸の感覚をつかむ練習になる。声量アップや楽な発声、ピッチやアタックをよくする効果がある。
- 腹式呼吸
-
主に横隔膜(肺の下にある筋肉)を動かして行う呼吸法。
息を吸うときに横隔膜を下げて空気を取り込むためお腹が膨らむのが特徴。一度にたくさんの空気を取り込むことができる。就寝時などリラックスしているときに行っている深い呼吸。
胸式呼吸
- ロングブレス
-
一定量の息をできるだけ長く吐き続ける呼吸法。
安定した歌唱、声量のコントロール、歌唱表現の向上などの効果がある。腹式呼吸の習得が必須。ダイエットやストレス解消などボイトレ以外の効果もあり。
練習
- 換声点
-
地声(チェストボイス)から裏声(ファルセット)へ、またはその逆に変わる声域のこと。
音程が安定しづらい声域のため、スムーズに切り替えられるようにすることがボイトレ上達のポイントとなる。
- 声帯閉鎖
-
発声時に声帯を一時的に閉じて空気の流れを遮断するボイストレーニングの一つ。
声帯を適切に閉じることで、声の漏れや声質の悪化、声が出にくくなることを防ぐ。高音やパワフルな発声、表現力の向上など高いレベルのパフォーマンスにつなげられる。
- タングトリル
-
「トゥルルル」と舌を震わせながら発音するボイストレーニングの一つ。
いわゆる「巻き舌」のこと。舌の力みがほぐれて発声が安定し、表現力アップや滑舌がよくなる効果もある。声帯のウォーミングアップとして最適。
- 鼻腔共鳴
-
鼻の奥にある空洞「鼻腔」で声を共鳴させるボイストレーニングの一つ。
通常の発声よりも響きが良くなる効果がある。声に奥行きや温かみを持たせることができ、魅力的な歌声になる。喉を痛めにくくする、ミックスボイスができるようになるなどのメリットもある。
- ブリッジ
-
地声から裏声に切り替わる音域のこと。声がひっくり返ったり息漏れが多くなったりする音域。
地声と裏声の切り替えをスムーズに繋げられると高音域を発声しやすくなる。ミックスボイスの習得に不可欠。
- リップトリル
-
唇を閉じた状態で息を吐きブルブルと唇を震わせながら発声するボイストレーニングの一つ。
音程を取りやすくする、声量のコントロール・安定、喉の負担を抑えるなどの効果がある。
リップロールと同意義だが、震える音を強調したいときに使われる場合もある。
リップロール
- リップロール
-
唇を閉じた状態で息を吐きブルブルと唇を震わせながら発声するボイストレーニングの一つ。
音程を取りやすくする、声量のコントロール・安定、喉の負担を抑えるなどの効果がある。ウォーミングアップとしても使われる。
リップトリル
声
- アルト
-
女性の声域の中で低い音域のパート。
豊かな響きと落ち着いた深みのある声が特徴。合唱ではソプラノやメゾソプラノのメロディを支える重要なパートを担当することが多い。ソプラノの高音域に対してアルトが低音域を歌うことで曲全体を安定させる効果がある。
- ウィスパーボイス
-
ささやき声のように発声する声のこと。
声帯を完全に閉じきらず、息を多めに漏らすことで「切なさ」「儚さ」「柔らかさ」などの感情を表現できるテクニック。特にバラードで好まれる傾向がある。
- 歌声
-
歌を歌う声のこと。
息をコントロールして発声し、音程やリズムを調整しながら曲を表現する。より魅力的に表現するためにボイストレーニングを行い発声テクニックを習得することもある。
- 裏声
-
地声から喚声点(地声から裏声に切り替わる点)を越えて裏返った声のこと。
歌唱では高音域の声全般をさし、「ファルセット」「ヘッドボイス」「ミドルボイス(ミックスボイス)」の3種類がある。
ヘッドボイス・ファルセット
- エッジボイス
-
声帯が閉じた状態で「あ゛あ゛あ゛」と発声する声のこと。
低い声に濁点をつけたような声で、ブツブツと聞こえる音が揚げ物の油の音に似ているため、別名「ボーカルフライ」とも呼ばれている。声帯閉鎖トレーニングとして使われ、「切なさ」や「悲しさ」などの感情を表現するテクニックとしても使われる。
- シャウトボイス
-
声を意図的に歪ませて叫ぶように発声する歌唱法。
特にロックやメタルなどのジャンルで用いられ、激しさや怒りなどの感情表現に使われることが多い。「フライ・スクリーム」と「フォールス・コード・スクリーム」の2種類にわけられる。
- 絶対音感
-
音を聞いたときに、基準となる音と比較することなくその音名を正確に判断できる能力のこと。
生まれ持った能力ともいわれるが、幼少期に適切なトレーニングを行うことで習得することも可能。楽器の音だけでなく日常生活の音も音名として認識できることがある。
- 相対音感
-
基準となる音を聞いて、その音の高低差から音名を判断できる能力のこと。
音程を正しく把握するために重要な能力で、トレーニングによって習得することができる。
- ソプラノ
-
女性の声域の中で最も高い音域のパート。
高音域を美しく響かせて華やかな印象を与える特徴がある。オペラのアリアや歌曲など高音の華やかさが求められる曲で活躍。合唱曲では透明なトーンと高い表現力が必要とされる。
- 地声
-
普段の自然な会話で使う声のこと。その人が持って生まれた声。
比較的トーンが低く、声帯全体を震わせて発声するため、張りや力強さがあり響きやすい特徴がある。文章を朗読するときにも使われる。
チェストボイス
- チェストボイス
-
歌唱における低音域の発声方法で、声を胸に響かせる声のこと。
一般的に「地声」と呼ばれるが、いわゆる会話での「地声」とは異なる。声帯の振動が胸に共鳴することで芯のある声になる。特に低音域の発声で使われ、力強く安定感のある響きが特徴。
地声
- テノール
-
男性の声域の中で比較的高い音域のパート。
華やかで若々しくエネルギッシュな印象で、高音域の力強い歌声が特徴。オペラでは主役級の役割を担うことが多く、合唱ではメロディーを歌ったり、ハーモニーを形成したりする役割がある。
- のど声
-
一定の音程を保ちながら、できるだけ長く発声し続ける歌唱方法。
声を長く伸ばすテクニックで、曲のサビやフレーズの終わりなどで感情を込めて歌う際に使われることが多い。難易度の高いテクニック。
- ハイトーンボイス
-
地声で出せる最も高い音域の声のこと。
生まれつきの声質の場合もあるが、ボイストレーニングで地声の音域を広げて習得することも可能。歌唱の場合は、濁りのないクリアな高音域で力強く歌い上げるテクニックとして使われる。
- ハスキーボイス
-
「かすれ声」「しゃがれ声」といわれる、ざらついた質感をもつ声のこと。
声帯が完全に閉じずにわずかな隙間から息が漏れることで生まれる独特の響きが特徴。生まれつきの声質の場合もあるが、ボイストレーニングで習得することも可能。ジャズやブルースなどのジャンルで好まれることが多い。
- ハミング
-
口を開けずに歌うこと。
歌詞を歌わずに「んー」という音で音程をなぞる歌唱方法。喉に負担をかけずに発声の練習ができ、共鳴感覚を身につけることができるメリットがある。口を少し開けて歌う鼻歌とは異なる。
- ファルセット
-
裏声の一種で、歌うときに高音域を出すために使われる発声方法。
息を多く含み、ふんわりとした柔らかい声質が特徴。繊細な声を表現するのに適しており、バラードや切ない曲などで使われることが多い。
ヘッドボイス・裏声
- ヘッドボイス
-
声を頭に響かせるようにして発声する高音域の声のこと。
声帯が閉じているので息漏れが少なく、地声に近い力強さや芯のある声で、裏声のような高音域を出す発声法。オペラやミュージカルなどで使われることが多い。
裏声・ファルセット
- ホイッスルボイス
-
人が発声できる最も高い音域の声のこと。
裏声よりもさらに高い音域で、口笛のような音に聞こえることから名付けられ「超高音発声」「超ハイトーン」とも呼ばれる。超高音かつクリーンな発声の「構音型」とデスボイスの一種「気流型」がある。
- ミックスボイス
-
地声(チェストボイス)と裏声(ファルセット)の中間の音域を滑らかにつなげる発声方法。
地声の強さで高い音域を出せるテクニックで、歌唱表現の幅を広げる重要なテクニックの一つ。ミドルボイスと同じ意味として使われることが多い。難易度の高いテクニック。
ミドルボイス
- ミドルボイス
-
地声(チェストボイス)と裏声(ファルセット)の中間の音域(E4〜B4の中音域)の声のこと。
地声の力強さと裏声のやわらかさを兼ね備えた、歌唱表現の幅を広げる重要なテクニックの一つ。ミックスボイスと同じ意味として使われることが多い。
ミックスボイス
- ロングトーン
-
一定の音程を保ちながら、できるだけ長く発声し続ける歌唱方法。
声を長く伸ばすテクニックで、曲のサビやフレーズの終わりなどで感情を込めて歌う際に使われることが多い。難易度の高いテクニック。
楽典
- イントロ
-
イントロダクションをより短くした言い方。
イントロダクションは「イントロ」と呼ばれることのほうが多い。楽曲の終わりを印象づける「アウトロ」と対照的な役割がある。
アウトロ
イントロダクション
- イントロダクション
-
楽曲の冒頭部分、一般的に歌が始まる前に演奏される部分を指す。
前奏や導入部とも呼ばれる。楽曲のテーマや世界観、リズムパターンを提示することで歌やメロディーへスムーズにつなげる役割がある。
イントロ
- エイトビート
-
1小節を8等分して8つの8分音符で区切ったリズムのこと。
ロックやポップスなど幅広いジャンルの音楽で使われる。基本単位となるリズム。2拍目と4拍目にアクセントがつけられるのが一般的。8分音符よりもさらに細かい16分音符で区切ったリズムは16ビートという。
- オクターブ
-
ある音から数えて8番目の音、またはその2つの音の間隔のこと。
例えばドから上または下に数えて8番目のドの音、あるいはその間隔。2オクターブはさらに次のドまでを指す。音名は同じだが、周波数が2倍または1/2になる。
- 音域
-
人が発声できる音の高さの範囲のこと。
成人の一般的な音域は1オクターブから1オクターブ半といわれている。音域が広いと幅広いジャンルの曲が歌えて表現力も向上。ボイストレーニングにより音域を広げることが可能。
- 音程
-
異なる2つの音の高さの差。
ドからミ、ミからドなど音が上がったり下がったりする動きのこと。音程を正しく捉え発声のコントロールができると、メロディーを正確に理解して歌うことができる。また音程を意識することで、音楽の雰囲気をより深く理解できるようになる。
ピッチ
- スコア
-
楽譜のこと。
オーケストラなど大編成の楽曲を構成する、すべてのパートの楽譜が縦に並べて書かれた楽譜は「フルスコア」「総譜(そうふ)」、バンドで演奏する楽器のパートの楽譜をまとめたものは「バンドスコア」とも呼ばれる。
- ピッチ
-
ある1つの音の高さのこと。
Hz(ヘルツ)という単位の周波数で表される絶対的な音の高さ。周波数が大きいと音は高く、小さいと音は低くなる。同じ音名でも周波数がずれると、わずかに低くあるいは高く聞こえる。
ピッチが合う=周波数がぴったり合った音が出せていること。
音程
技巧
- アカペラ
-
楽器を使わずに声だけで演奏する音楽。
ハーモニーやリズム、音色、ビートボックスなどを駆使して音楽を表現。ポップス、ロック、ジャズ、クラシックなどさまざまなジャンルの音楽を演奏することができる。合唱だけでなく、独唱、重唱も含まれる。
- アクセント
-
声を波打つように揺らす歌唱法で、表現力豊かに歌うためのテクニック。
ロングトーンの際に使用され、音程をわずかに上下に揺らすことで音を美しく響かせる。主にフレーズの終わりなどで使われる。1秒間に6回の揺れが心地よく聞こえるといわれている。
- アコースティック
-
電気的な機器を使用しない楽器本来の音のこと。
エレクトリックギターやエレクトリックベースなどの電気楽器を使用した演奏に対して、ピアノやアコースティックギターなどで演奏するスタイルやジャンルのこと。
- アシッドジャズ
-
アメリカの黒人音楽をルーツに発展した音楽ジャンル。
その場の雰囲気や演奏者の感情を、楽譜にないメロディーで反映させる「即興演奏(アドリブ)」が重視される。また複雑なコード進行やブルーノート(半音低い音程)の使用、スイングと呼ばれる独特のリズムも特徴。
ジャズ
- アフタービート
-
小節内の弱拍(偶数拍)にアクセントを置くリズムのこと。
4分の4拍子の場合、1拍目と3拍目が強拍で、2拍目と4拍目が弱拍(偶数拍)となる。特にジャズやロックなどのジャンルで弱拍(偶数拍)にアクセントを置くリズムがよく使われる。
バックビート
- アンサンブル
-
合奏や合唱など2人以上の演奏者が一緒に演奏する形態。
小規模な演奏形態を指すことが多い。また演奏のバランスや統一感を表現する言葉として使われることもある。(例 アンサンブルが良い)
- アンプラグド
-
直訳の「プラグを抜いた」という意味から、電気楽器やアンプを使わない、アコースティック楽器のみで演奏するスタイルを指す。
アコースティックギター、ピアノ、ウッドベース、ドラムなど電気を必要としない楽器が使われるのが特徴。
- インストゥルメンタル
-
歌やボーカルが入っていない、楽器のみで演奏される楽曲を指す。インストと略されることも多い。
クラシック音楽から映画やテレビなどのBGM、リラクゼーション音楽など幅広いジャンルで使用される。ボーカル曲からボーカルパートを抜いた「オフボーカル」やカラオケ音源を指すこともある。
- オールディーズ
-
1950〜60年代にかけて流行したアメリカやイギリスなどのポピュラー音楽。
ロックンロール、ロカビリー、R&B、ポップスなどがある。「古き良き時代の音楽」「懐メロ」「定番曲」といったニュアンスでも使われる。
- カバー
-
すでに発表されている楽曲を別のアーティストが自分の解釈で演奏、歌唱、または編曲して発表することまたはその作品。
原曲の魅力を引き出す、新たな解釈を提示する、自分が感じた音楽性を表現するといった目的で行われることがある。
オリジナル
原曲
- カントリーミュージック
-
1950〜60年代にかけて流行したアメリカやイギリスなどのポピュラー音楽。
ロックンロール、ロカビリー、R&B、ポップスなどがある。「古き良き時代の音楽」「懐メロ」「定番曲」といったニュアンスでも使われる。
- グランジ
-
1980年代後半にシアトルを中心に流行したロック音楽のジャンル。
パンクやヘヴィメタルの影響を受けた、歪んだギターサウンド、社会へ反発や若者の心情を反映した、陰鬱で反抗的な歌詞が特徴。
- グルーヴ
-
リズムのノリのよさや心地よさ、それぞれのパートがしっかりと噛み合っている一体感をさす言葉。
音楽を聴いて身体を動かしたくなるような、言葉や理論では説明できない高揚感や感覚のこと。ジャズやファンク、ソウル、R&Bなどのブラックミュージックで用いられることが多い。
- クワイア
-
複数の歌手が一緒に歌う合唱。
コーラスよりも宗教的な要素が強く、特に教会音楽の讃美歌やゴスペルコーラスの合唱隊、聖歌隊を指すことが多い。またDTMではシンセサイザーなどの音色を指す言葉として使われる。
- ゲネプロ
-
本番と同じ環境で、最初から最後まで通して行われるリハーサルのこと。
音楽では、コンサートやオペラなどで行われる。演奏者だけでなく、照明、音響、舞台スタッフ、オーケストラの場合は指揮者も含めたすべての関係者が参加し、本番と同じように演奏する。
- ゴスペル
-
楽器を使わずに声だけで演奏する音楽。
ハーモニーやリズム、音色、ビートボックスなどを駆使して音楽を表現。ポップス、ロック、ジャズ、クラシックなどさまざまなジャンルの音楽を演奏することができる。合唱だけでなく、独唱、重唱も含まれる。
- ジャズ
-
アメリカの黒人音楽をルーツに発展した音楽ジャンル。
その場の雰囲気や演奏者の感情を、楽譜にないメロディーで反映させる「即興演奏(アドリブ)」が重視される。また複雑なコード進行やブルーノート(半音低い音程)の使用、スイングと呼ばれる独特のリズムも特徴。
アシッドジャズ
- ソウルミュージック
-
1950年代にアメリカで生まれた音楽ジャンル。
アフリカ系アメリカ音楽であるゴスペルやブルース、R&Bなどを融合させた音楽で、力強いボーカルとリズムが特徴。ソウルと略されることもある。
- テクノ
-
アメリカのデトロイトで生まれた電子音楽のジャンル。テクノポップの略。
シンセサイザーやリズムマシンといった電子楽器を使った反復的なリズム、無機質で機械的なサウンドが特徴。クラブや音楽フェスティバルでプレイされることも多い。
- デモテープ
-
音楽制作の過程で、作曲者や演奏者が自身の楽曲を関係者に評価してもらうために作成した音源(録音物)のこと。
オーディション審査やレコード会社への売り込みで使用されるほか、作曲者がアレンジや構成を伝えるために使われる場合もある。
- ドゥ・ワップ
-
1970年代にアメリカのニューヨークで生まれ発展した歌唱法で、ヒップホップ音楽要素の一つ。
リズミカルに早口で話すように歌うのが特徴。韻を踏んで言葉のリズムを強調したり、言葉遊びをしたりして、社会問題や政治的なメッセージ、日常のできごと、感情などを表現することが多い。
- ビブラート
-
声を波打つように揺らす歌唱法で、表現力豊かに歌うためのテクニック。
ロングトーンの際に使用され、音程をわずかに上下に揺らすことで音を美しく響かせる。主にフレーズの終わりなどで使われる。1秒間に6回の揺れが心地よく聞こえるといわれている。
- フェイク
-
原曲の範囲内でメロディーやリズムをアレンジして歌うテクニック。
歌の感情表現を豊かにしたり、個性を際立たせたりすることができる。リズムに変化を加える「リズムフェイク」、音程に少し変化を加える「メロディーフェイク」、しゃくりやこぶし、フォールなどを加える「装飾音フェイク」の3種類がある。
- ユニゾン
-
複数の人が同じ旋律を同時に演奏する、または歌うこと。
オクターブ違いもユニゾンとみなされる場合がある。音に厚みを持たせる、メロディーを強調するなど楽曲に力強さや深み、一体感を与える効果がある。
斉唱
斉奏
- ユーロビート
-
ヨーロッパで生まれたダンスミュージックの一種。
日本ではパラパラブームとともに独自に進化。電子楽器を用いた4拍子を繰り返すリズムや、キャッチーで覚えやすいメロディーが特徴。
- ラップ
-
1970年代にアメリカのニューヨークで生まれ発展した歌唱法で、ヒップホップ音楽要素の一つ。
リズミカルに早口で話すように歌うのが特徴。韻を踏んで言葉のリズムを強調したり、言葉遊びをしたりして、社会問題や政治的なメッセージ、日常のできごと、感情などを表現することが多い。
- リテイク
-
音楽制作の過程で、レコーディングや録音をやり直すこと。
演奏のミスや技術的な問題で行う場合もあるが、全体のバランス調整や、より良い楽曲を制作するために行うこともある。
ファーストテイク
- ロック
-
1950年代にアメリカで生まれた音楽ジャンル。
エレキギターを中心としたバンド形式で演奏されるのが一般的。体を揺さぶるような躍動感や、力強いビートを持つのが特徴。社会への反発や自由への渇望など若者の反骨精神や自己表現などメッセージ性の高い歌詞の楽曲も多い。
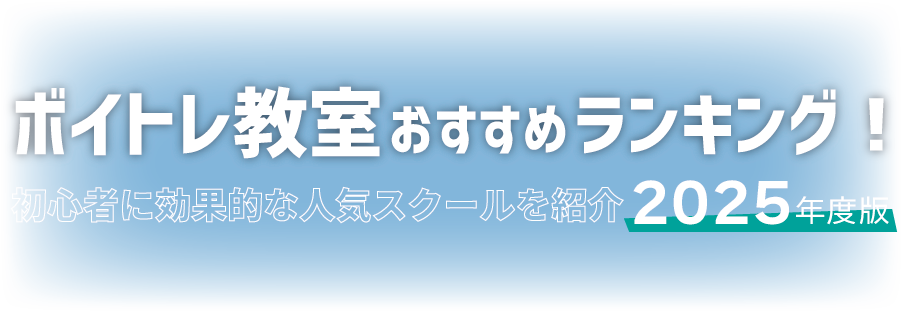
 EYS音楽教室
EYS音楽教室
 USボーカル教室
USボーカル教室 アバロンミュージックスクール
アバロンミュージックスクール